
東京都内のデザイン事務所で経験を積んだ後、独立し、現在はイラストレーター兼グラフィックデザイナーとして活躍する富樫祐介(とがし?ゆうすけ)さん。コロナ禍をきっかけに山梨県大月市へ移住し、小さい頃から好きだった昆虫や魚を観察しながら、それを自らのイラストの仕事に活かしています。生き物の魅力を伝えるために取り入れたという富樫さんならではのフラットデザインは、どのようにして生まれたのでしょう。大学時代の学びと合わせてお聞きしました。
? ? ?
昆虫への興味があらゆる仕事に発展
――富樫さんのお仕事内容について教えてください
富樫:イラストの方に関しては、書籍の装丁だったりその中での図説のイラスト、あと雑誌の挿絵やパッケージなどの仕事があります。また最近では僕の昆虫のイラストがフィギュアやテキスタイルになったり、それからオリジナルグッズもつくっていて、自然科学系のイベントなどに出展した際はお客さんと直接話しながら販売したりしています。
デザインの方については、本のデザインやロゴマークなど広告的なものが中心ですね。最近はイラストの仕事が多くなってきたので、バランスとしてはイラストが7割、デザインが3割と昔に比べて逆転してきました。

――もともとは都内でデザインの仕事をされていたそうですね
富樫:表参道にあるエディトリアルデザインの事務所で、当時は『週刊パーゴルフ』というゴルフ雑誌や、ベネッセ『こどもちゃれんじ』の教材などを担当していました。その後、次第に地方のデザインに興味が湧いてきて、退社後、秋田のデザイン会社に入ったんですけど、そこで出会った現在の妻が「東京でデザインしてみたい」ということだったので、僕も東京に戻ってフリーでデザイナーをする流れになって。でもそうこうしているうちにコロナ禍でオンラインでの打ち合わせが多くなってきて、それを機に山梨県大月市で見つけた一軒家へ家族と引っ越しました。
僕は昆虫とか魚といった生き物を実際にフィールドに見に行って観察することを大事にしているので、やっぱり自然に近いところがいいな、と。山形県最上地方の信号機もないようなところで育って、小さい頃は川に行って魚を捕まえたり、釣りをしたり、オニヤンマを捕まえたり。そうやって過ごしてきたので、自然と生き物を描くようになっていきました。


富樫さんが出展した『昆虫大学2024 in 浅草橋』は、昆虫の魅力をプロから学べるというイベント。大学の校章は富樫さんがデザインしたもの。会場は昆虫愛好家や親子連れなど多くの人で賑わっていた。
――イラストレーターというお仕事を意識するようになったのはいつ頃から?
富樫:絵を描く仕事をしたいなとはずっと思っていましたが、将来を考えていく中でだんだん広告とかパッケージのように伝達ツールとして人の社会の中に組み込まれている、視覚的なサインに興味が向くようになりました。
その後、グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所に入って、イラストレーターさんに仕事を依頼していく中で、「やっぱり物事を柔らかく楽しく伝えられて、そこに自分の世界観も反映できるイラストの仕事ってすごくいいな」と思い始めて、それがイラストレーターを志すきっかけになりました。
ちょうどSNSが流行ってきた時代だったこともあり、デザインの仕事をしながらも定期的にイラストをアップすることを決めて描き続けていたら、それが人の目に留まるようになって、時々バズったりしながら徐々にイラストの仕事が増えて、自然にイラストレーターになっていったという感じです。



――今まで携わってきたお仕事の中で、特に印象に残っているものは?
富樫:2年ほど前に担当させてもらった『学研の図鑑LIVE』の仕事ですね。その図鑑の大きな特徴は、生きた昆虫を全部白バックで撮影するというものなんですけど、僕は昆虫の中でもトンボが好きで。そしたら総監修の丸山宗利(まるやま?むねとし)先生から「トンボのページを担当してくれないか」と連絡をいただいて、トンボの採集から撮影、生態の執筆、そして付録のポスターのイラストまでを担当することになったんです。
トンボだけでその種類は200を超えますし、生息地も川だったり湿地だったり山だったり、また現れる場所も短い期間で変わっていくので、それを追いかけて北海道から四国、山口県あたりまで一年かけて回りました。まさかデザインを勉強した先に、小さい頃から好きで見ていた昆虫図鑑に携われる仕事が待っているとは思っていなかったので、すごく感慨深かったです。

情報の取捨選択から生まれた独自のデザイン
――芸工大のグラフィックデザイン学科でデザインを学ぼうと思ったきっかけは?
富樫:実を言うと、僕は芸工大に入る前に仙台のデザイン系の専門学校を卒業しているんですけど、その当時はデザインに対して「見た目がかっこよければいい」とか「かわいければいい」と思っていたところがあって、「技術を習得すればなんとかなるだろう」と考えていました。でも就活する中で「デザインに大事なのは、何が問題なのかを読み取ったり、それを表現する力なんじゃないか」っていうことに遅まきながら気付いて。もちろん芸工大の存在は前から知っていましたし、東北のことも好きだったので、地元のことを掘り下げつつデザインの勉強ができたらと思い、入学しました。
――実際に学んでみて、どのようなところに専門学校との違いを感じましたか?
富樫:専門学校では技術面を学ぶことが多かったんですけど、芸工大に入ってみて、一見関係ないようなワークショップから得る考え方や感受性がとても大事なことに気が付きました。
所属していた大竹左紀斗(おおたけ?さきと)先生※のエディトリアルデザインのゼミで、チャートやダイヤグラムを使って細かい情報を視覚的に一つにまとめて分かりやすく表現することを学び、そこで知ったのが、何が大事で結果はどうで、何を省略して、それをどう表現すると楽しく伝えられるのかという取捨選択の考え方。それが今、生き物のイラストを描く上ですごく活きていると感じます。
※エディトリアル?デザイナー。2023年までグラフィックデザイン学科で教鞭を執る。

普段は昆虫を描く仕事が多いんですけど、「昆虫は苦手」って人も結構多くて(笑)。でも僕は小さい時から「魅力的なのにな、かっこいいのにな」と思って昆虫を見てきたので、その良さを伝えたいという思いからデザインの学びで培った引き算?足し算が活かされ、今の僕のメインタッチであるフラットデザインのイラストが生まれたと感じています。
ただ、そぎ落としたタッチにするにも最初に細密画をちゃんと描けていることが大切で、あくまでもリアルタッチのイラストがすべての基礎にはなっています。

――より多くの人に昆虫の魅力を伝えたい、という思いからたどり着いたタッチなんですね
富樫:そうですね。あえて平面的なデザインにして色や形をパリッと明快にすることで、昆虫への苦手意識を少しでもなくせたらいいなと思って。でもデフォルメしすぎてキャラクターのようになってしまっては生き物としての本来の魅力が伝わらないので、専門家の方が見ても「あの生き物だよね」と分かるくらい、その特徴を外さないようにして描くことを大事にしています。昨年、京都で開催された『国際昆虫学会議』に呼んでいただき、物販コーナーでグッズ販売してきたんですけど、「昆虫の特徴がちゃんと捉えられていていいね」と言って世界中の研究者の方が買って行ってくれて、すごくやりがいを感じましたし自信にもつながりました。

ちなみに、昆虫に恐れを感じさせないっていうところを大切にしているのにはもう一つ理由があって、僕自身が「得体の知れないものってなんか怖いな」っていうのを経験しているからなんですよね。実はもともと毛虫が苦手で、見ると前に進めなくなるくらい……(笑)。でも7~8年前に毛虫のイラストを描こうと思って細かいところまで観察したら、その構造が見えてくるにつれ苦手意識が薄らいできて、今ではかわいいなと思えています。
大竹先生は常々、例えば落ちているゴミにもどこから来たものかのヒントがあって、掘り下げることでそのルーツが分かるとただのゴミも物語に見えてくるという話をしていたんですけど、まさにそういうことなのかなって思いました。
――今後、挑戦してみたいことはありますか?
富樫:生き物の生態や環境をテーマにした絵本を描いてみたいですね。というのも、最近は開発や里山の人口減少、外来種の影響など、いろんな方面から身近な生き物が減ってきていて、気付いたらもう絶滅してる、みたいなことも起こっていて。なので、そういうのを子どもたちに伝えるためにも生き物の環境を守ることにつながる導入として絵本が描ければ、と思っています。子どもが生まれてからは、より一層そう考えるようになりました。
――それでは最後に受験生へメッセージをお願いします
富樫:やっぱり描き続けるというか、好きなことをずっと続けていくって本当に大事なことだと思います。その上で自分の興味だけに執着せず、いろんなものを見るっていうことも大事にしてほしいですね。僕も昆虫や魚が好きで、途中ゴルフ雑誌のような関係ないものを仕事にしつつも、ずっとイラストを描き続けてきて。でも結局、そういったデザインの仕事が今につながって自分の力になっていることを考えると、関係ないものなんてないんだなって。それからインターネットで検索するだけでなく、自分で体験することも大切にしながら、大学で遠慮なく“好き”を追求していってもらいたいです。

? ? ?
芸工大で受けた、マタギや田植え、養蚕など自然環境に関わる実体験の伴った授業が印象に残っているという富樫さん。所属していた釣りサークルでの活動を含め、東北の自然との関わりを深められた四年間だったと言います。さらに卒業制作では、最上川をテーマに源流から河口まで実地調査を行い、その結果をチャートやダイヤグラムを用いて視覚的に表現。見事、最優秀賞を受賞しました。楽しく伝えるために必要な情報の取捨選択の考え方、そして得体の知れないものでも観察し理解することで薄れていく恐怖心や苦手意識。それらを学んだからこそ生まれた富樫さんのフラットデザインは、フィギュアや服などさまざまなアイテムのデザインに採用されており、今後もその活躍から目が離せません。
(撮影:佐々木里菜、取材:渡辺志織、入試課?須貝)
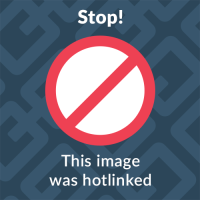
東北芸術工科大学 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-
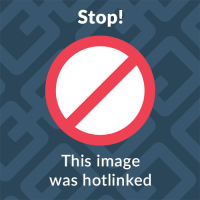
2020.12.18|インタビュー
今さら聞けない! 世界遺産登録を目指す「北海道?北東北の縄文遺跡群」ってなんだ?
#教職員#歴史遺産 -
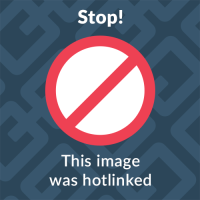
2021.07.15|インタビュー
学生相談室はどんな悩みもウェルカム。まずはあなたの「声」を聞かせてほしい/臨床心理士?今野仁博 准教授
#万博体育投注_万博体育彩票-下载app登录#教職員 -
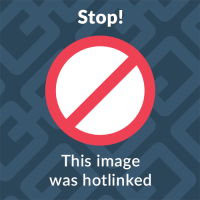
2024.02.09|インタビュー
東北から東京へ。芸工大が取り組む東京3展覧会の特色と学び/青山 ひろゆき(美術科長)×三瀬 夏之介(大学院芸術工学研究科長、美術館大学センター長)× 深井 聡一郎(大学院芸術文化専攻長)
#DOUBLE ANNUAL#卒業生#在学生#大学院#展覧会#教職員#美術科




