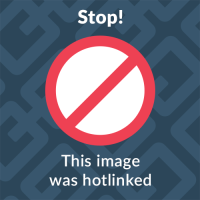
【前編】卒業生作家たちに聞く、学生時代から現在に至る道のり/「TUAD ART-LINKS」トークイベントレポート 城下透子(卒業生ライター)
レポート 2024.03.27|
#卒業生#工芸#彫刻#教職員#日本画芸工大を卒業した作家たちを応援するプロジェクト「TUAD ART-LINKS」。 第9回目の開催となる今年度は、新宿髙島屋をはじめとする東京都内5つの画廊で、卒業生たちによる作品の展示?販売が行われました。
今回は、新宿髙島屋会場にて実施されたトークイベントの内容をお届けします。 登壇されたのは、大野菜々子さん(日本画)、五月女晴佳さん(工芸)、外丸 治さん(彫刻)、古田和子さん(日本画)の4名。 三瀬夏之介教授と深井聡一郎教授をまじえ、学生時代の思い出や、卒業後の作家生活についてお話しいただきました。
? ? ?
来年でいよいよ10回目を迎える「ART-LINKS」
三瀬:今回は、東北芸術工科大学の卒業生を応援するプログラム「TUAD ART-LINKS」のいち会場である、新宿髙島屋からお届けします。
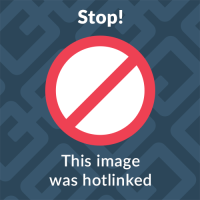
三瀬:東北芸術工科大学は、公設民営型の大学として1992年に開学しました。山形県と山形市が、市内の環境の良い土地に建物を建ててくれて、そこを民が運営するという構造で。京都芸術大学を姉妹校とし、京都と東北からさまざまな芸術活動を興していく、というコンセプトで作られた大学です。
実は一昨年に、開学30周年を迎えました。これまで僕たちは「若い大学」と言っていたんですけど、30年も経てば、中堅の大学に入ってきたなというところですね。アーティストとして活躍したり、あるいは教員として戻ってきたり、さまざまなステージで活躍をしている卒業生たちがいます。
そういった卒業生の制作発表を支援していくために作られたプログラムが、この「ART-LINKS」という卒業生による展覧会です。今年は9回目ということで、いよいよ来年が10回という区切りになりますね。もう9年ほど卒業生たちを支援しつづけてきていることになります。当初から首都圏の貸ギャラリーにご協力をいただいてきましたが、徐々に「芸工大の卒業生たちを全面的に支援したい」という企画展の方向になり、近年は、作家としての販売のマナーや、作品の値段のつけ方など、作家活動に大切なものまで教えてもらえる、スクールのような場所に育ってきています。
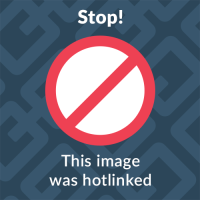
三瀬:また「ART-LINKS」のもうひとつの側面として、卒業生を精神的に支える役割もあります。僕も深井先生も美大を出てすぐに作家としての活動をスタートさせていますが、大学を卒業してしばらくの時期が一番しんどい、と身をもって実感していたんです。社会人になると、学生時代は当たり前であった、贅沢な広いアトリエはなくなります。また、日々アートの話をしていた仲間も近くにはいなくなります。
そういった孤独のなかで活動を続ける社会人作家を応援してあげたい、という想いから、大学の校友会と卒業生後援会が支援して「ART-LINKS」の活動を行っています。
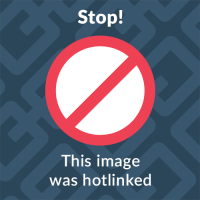
トークイベント会場となった新宿髙島屋の様子
三瀬:今年度は、ここ新宿髙島屋を含めて5会場で11名が参加しています。ぜひこのあと、ほかの会場も周っていただけたら嬉しいです。本来、髙島屋で作品を展示するというのは、作家として非常にキャリアを積んだうえでのゴールともいえるほどのことなんです。今回は、そんな会場を若手作家の展示会場として使わせていただいています。「ここでチャンスをつかんでほしい」という想いを込めて、今回はこの4人の作家が選ばれました。今日は彼らに、学生時代は山形でどのような日々を過ごしてきたのか、今はどこで過ごして、どんなふうに気持ちが変わり制作しているのか、変わらないことはなにか……。そういったことを聞いていければと思います。
「地域とつながり、制作する」ことへの想い
三瀬:まずは大野さんからお願いします。
大野:大野菜々子と申します。出身は秋田県で、今は東京に住んでいます。
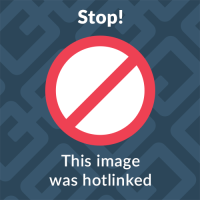
大野菜々子さん(写真中央)
大野:私が日本画コースに入学したのは2011年、ちょうど東日本大震災が起きた年でした。本来の入学時期は4月だったんですけど、3月に起きた震災の影響で入学が遅れてしまって。実際に大学生活が始まったのは、ゴールデンウイークの少し前の時期でした。
その関係でカリキュラムも例年と少し違いましたね。毎年の恒例だったスケッチ旅行がなかったのもありますし、授業内容もやはり震災と関連したものが多く、いろいろな影響があったので、ほかの学年とは違うスタートダッシュだったかなと思います。
そういったこともあってか、私たちの学年では「なぜ、絵を描くのか」「なぜ、制作するのか」というのが、非常に強いテーマとして共通していました。
三瀬:スタートダッシュというか、そもそもダッシュを切れなかった、すごく大変な時期でしたね。僕が関西から山形の芸工大に赴任したのが2009年で、「東北って面白い、楽しい」と数年ほど過ごしていたら、あの震災が急に起きて……。大野さんの学年は、僕も思い入れが非常に強いです。「入学どころか、東北がダメになってしまうのではないか」という状況で。そんな大変ななか、入ってきてくれた学年です。
深井:僕は同じ年に教員として赴任したので、大野さんと同期ですよ。あの学年って、今も作家として活動している卒業生がかなり多いんですよね。「絶対にやめない」という意思がすごく強い。被災地へボランティアに走って、ボランティアからまた美術に戻ってきた子もいたし、ボランティアがメインになって活動している子もいるし。「何者かになる」という意思をもっている学年だったと思います。
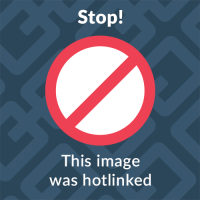
三瀬:大野さんは日本画コースで、僕がずっと見てきた学生なんですけど、卒業制作の最優秀賞を受賞していましたよね。出身地である秋田の男鹿半島をテーマにした作品でした。
大野:男鹿半島は、なまはげがすごく有名なんですけど、それゆえになまはげが観光化してしまっていて。観光のキャラクターとして扱われるなまはげというのが、私にとってすごく違和感があったんです。ただ同時に、私は地元のことをよく考えたことがなかったので、改めて自分の生まれた場所と向き合いたいと思って、なまはげについて知ろうとしました。なまはげの活動を行っている団体の方に取材したり、歴史を調べたりなどして、なまはげの本質的とは、なんなのか? を追っていましたね。
そうしていくうち、実は世界中に、仮面をつけて一軒一軒の家をめぐっていく行事があるということを知りました。ローカルなものだと思っていた文化が、実は世界に広がっていて、つながっていた。世界中にあるということは、“仮面”あるいはそういった文化が、人間の源流というか、人々の根底にあるイメージに触れるものじゃないかな、と思ったんです。 それで卒業制作では、秋田のなまはげだけでなく、世界中にある仮面のモチーフを集めながら構成を考えて、私の思うなまはげ的な存在を描きました。
三瀬:ここにいる4人はみな、芸工大の大学院を出ているんですけど、芸工大の院には“大学院レビュー”という名物イベントがあります。院生たちが領域を超えて中間発表して、意見を交換し合うんですね。たとえば、工芸の学生にプロダクトデザインの学生が意見を言ったりとか、あるいは大野さんのような民俗学的なアプローチで絵を描いている学生に、歴史遺産を研究している学生が話をしたりとか。非常にコンパクトな大学院なので、研究領域にとらわれない交流が生まれます。
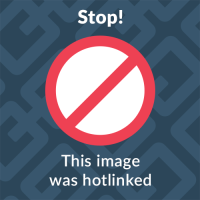
大学で開催されている「大学院レビュー」の様子。様々な専攻の学生が集まり、発表と意見交換が行われる。
三瀬:大野さんは、今も地域に根ざしたモチーフで制作しているけれど、学生時代にこういった領域を超えた交流を考えるきっかけってあったんでしょうか?
大野:在学中は「東北画は可能か?」※という、三瀬先生が主催されているチュートリアルに参加させていただいていて、そこの経験が大きかったと思います。領域の前提を越えて、集まる活動ですね。アトリエから外に出て、地域の方のお話を聞いて、そこで感じたことをもとに作品を作る、というのをやっていました。そういった、外にどんどん広がっていく活動、地域とつながっていく活動が作品にすごく影響を与えてくれたな、とは感じています。
※「東北画は可能か?」は本学のチュートリアル活動(教員が主体となり、自身の専門性や研究活動などの特徴を生かして行われる課外活動)の一つ。東北における美術の可能性をフィールドワーク、作品制作、展覧会、イベントなどを通じて追求するプロジェクト。
三瀬:さっきの震災の話とも少し関連していて。この学年は、ある意味「地域とつながる」、「地域を復興する」という期待を受けていた立場でもあったのですが、そういった面で、地域に入り込んでものを作っていく活動は、どうでしたか?
大野:地域の方とお話をして、それを作品にする行為は、ただ「交流して楽しい」とか、作品を作って喜んでもらうだけのものではないんだな、と気づきました。
ある種、その地域で起きた話を利用してしまう……、ということにつながる怖さもあると思います。その側面とどう向き合っていくか、それを背負ったうえで、どう作品を作っていくか、がとても重要なんですよね。
それも含め、“作品を作る”ということ自体、責任を持たなければならない行為なんだな、と強く学びました。
三瀬:秋田で生まれ山形に来て、今は東京に住んで作品を作っていますよね。今回の作品はすべて新作。頑張りましたね。この作品群には、大野さんの抱いているイメージはどんなふうに表れているんでしょう?
大野:やはり「描こう」と思う原動力になるものや、モチーフは、山形や秋田の自然だったり、そこで体験したものだったり、ですね。
大学を卒業して、東京に来てからは「作家になる」という意識をもったことで「鑑賞者の方に、自分のなかにあるものをどのように伝えるのか」を大切に考えるようになりました。
学生の頃は「何を表現するのか」「自分はどうしたいのか」と、自分のことでいっぱいだったんですけど、東京に来てからはいったんそれが落ち着いて。作家になるにあたっては、みなさんの目線、見方を意識できるようになりました。
三瀬:このなかで、大野さんの思い入れが強い作品は?
大野:一番大きい、この『切り抜きの山』という絵です。こちらのモチーフ自体は、山形市にある瀧山で。
※瀧山:蔵王連峰の山。古くから信仰の対象となっており、山頂からは蔵王連峰と山形盆地を見ることができる。
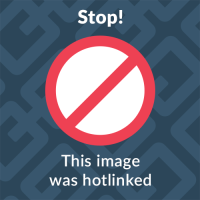
『切り抜きの山』
三瀬:瀧山なんですね。マッターホルンとかじゃなくて(笑)。
大野:そうなんです。実際の瀧山とは形もまったく違います。この作品は、写真をデジタル処理して、それを構成して描きました。というのも、私が毎日、通学するときに見ていた瀧山の実際のイメージを形にしようとしたときに、そのまま描いてもただ「きれいな風景画だな」という印象で終わってしまうな、と思ったんです。現代は、きれいな風景の画像がもうあふれていますから。
むしろそれをデジタルで再構成する、そして、さらに自分のなかの印象に近づけて描くほうが、私が感じているものをより表現できるのではないかと思いました。
三瀬:美しい画像的な風景を、上から荒々しく絵具で消すというのは、災害的なものというか。元々あったものが、あっという間の津波で別の意味を持つような印象を受けました。そういった感覚もあったりするんですか?
大野:そうですね。やっぱり、震災の年に入学した影響もありますし、震災だけでなく、毎年生きているだけでも大変なことがたくさんありますよね。猛暑や信じられないほどの大雨など……。日本に住んでいる以上は、そういうものと向き合わざるを得ないな、と思っています。
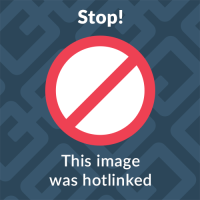
三瀬:芸工大の卒業制作展に行かれると分かるんですが、山を描いている学生が多くいます。実際、生活のなかにずっと山が見えるという、盆地なので。
だから、そこに住んでいる人たちは、山をいろいろな角度から見て解釈している。
今の世の中は、未曾有の出来事がたくさん起きている状況ですよね。そんななかで何かを祈るとか、信仰するというのが、昔の先祖返りのノスタルジー的なものではなく、今のものとして大野さんは描いているわけです。東京に住んでいる大野さんが、山に気持ちを寄せている。現代の作品でありながら、昔の考えも取り入れられていて、とても完成度の高い作品だなと思いました。
大野さんは、今後の制作活動のビジョンは何かありますか?
大野:いずれ、地元の秋田で何かやりたいですね。
コロナ禍でずっと帰省できなかったので、昨年久しぶりに帰ったんですけど、私の幼い頃と様子がかなり変わってしまっていたんです。秋田県全体で過疎が進んでいて、周りに若い方がなかなかいなくて。衰退が始まっているのを実感しました。その状況に対して、アートでできることが何かあるんじゃないかなと思うので、今は東京に住んでいますが、秋田でも活動したいなと思っています。
三瀬:距離と歳を重ねるごとに、故郷の見え方も変わりますよ。そういったこともいずれ起きてくると思います。
? ? ?
就職を経て気づいた、芸工大の教えの大切さ
三瀬:では、五月女(そおとめ)さんにも話を聞いてみましょう。
五月女:五月女晴佳です。よろしくお願いします。私は栃木県出身です。芸工大の工芸コースに2008年に入学して、大学院を卒業したのが2014年ですね。卒業後は、今の作品のコンセプトとなっている、お化粧品を扱う美容部員として就職しました。そのあと、ご縁あって芸工大の工芸コースで副手(事務職員)として働いたのち、石川県の「卯辰山工芸工房」という、工芸のプロフェッショナルな集団があるんですけど、そちらで3年間、勉強しながら働かせていただきました。今は金沢市で、専業作家1年目として活動しています。
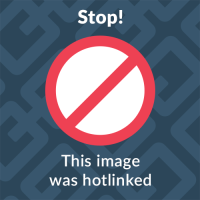
五月女晴佳さん
深井:大学や、大学院で印象に残っていることはありますか?
五月女:先ほど三瀬先生のお話にもあった“大学院レビュー”が勉強になりました。私が大学院に入ったのが、レビューが始まって2年目のぐらいの年だったんですよ。すごく衝撃的だったのは、このレビューを通じて「なんで自分は制作するのか」「工芸ってなんだ」という、本来ならばスタートである考え方を、恥ずかしながら、初めて大学院で学んだところですね。
レビューは非常に苦しかったんですけど、そういう世界に慣れなくてはいけない……、ということに気づいて、頑張ってついていきました。そこで学んだ結果は、卒業後にも生きています。たとえばお客様にプレゼンする際も、“自分は、なにをやっているのか”を言葉で表現しなければ作品の意図は伝わりませんよね。美容部員のお仕事で、お客様に化粧品を紹介する際も同様です。「製品を売る」というのは、根本的な考えとしては作品を制作していたときと変わらなかったんです。それを知ることができたのが、すごく良かったと思いますね。
深井:僕が学生だった当時は「作品で語れ」っていう風潮があって。僕は「それは、ちょっと違うな」とずっと思っていました。作品だけじゃなくて、言葉でも補っていかないといけないんじゃないかと。なので、芸工大の大学院に来て、レビューという制度が修了要件になっていると知り、素晴らしいなと思いました。僕が赴任したばかりのときはまだ「なんで言葉で語らなきゃいけないんだ」という疑問をぶつけてくる学生もいたんですけど、たぶん彼らも作家になると、その必要性に直面するわけです。なので、小さい大学院だからこそできる、こういう発表の場は重要だなと思っています。
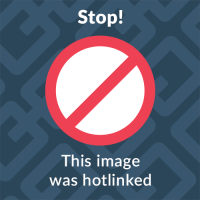
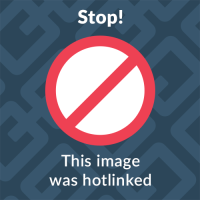
深井:五月女さんは、卯辰山工芸工房に行く前から良い作品を作っていたんですけど、今回の作品を見ると、また進化しているような気がします。卯辰山工房ではどんな経験を?
五月女:卯辰山工芸工房に来る人たちは、大学院も修了しているなど、ある程度技術がありましたね。周りがみんなライバルみたいな感じで、しのぎを削っていました。工房で技術を学ぶことももちろんあるのですが、どちらかというと「作家としてどう生きていくか」「自分の作品が、世の中にどう影響するか」など、技術以外の面を学ぶところだった印象です。そういった話を通じて、実際に作家としてご飯を食べていくための方法論も習得していきました。
深井:近代美術館の工芸館(現?国立工芸館)も東京から金沢に拠点を移しましたよね。
五月女:金沢市は工芸にすごく力を入れているな、というのは感じます。卯辰山工芸工房は、金沢市の助成金で成り立っているので。
毎月、支給される10万円を制作費に充てて、作品を売って生計を立てていくという仕組みなんですよ。市の税金をいただいて、立派な工房で制作できるんです。そういった場があることからも、文化レベルが高い土地だなと思います。
深井:そのまま居ついて作家になる人が多いんですよね。それを通して、若い層を厚くするのが実は一番の目的でもあり。ものすごく成功した事例だなと。山形でも同じようなことをやりたいとは思うけれど、なかなか難しいとは思います。
三瀬:金沢だと、地場産業との結びつきが強いので、それも成功の要因としてありそうですよね。地場産業の面でいうと、山形ってどうなんですかね?五月女さんの学生時代、そのあたりのつながりはあった?
五月女:私のいた当時は、山形の真室川というところにある工房で、上塗りの作業に参加させていただいたり、岩手県の浄法寺に研修に行ったりもしていました。あと、大学の裏に漆の木が普通に生えていて、漆かきの体験ができたのは、東北ならではだと思います。都会ではなかなかできないですよね。ただ、やはり金沢ほど地場産業とのつながりは強くなかった印象です。
深井:東北にも、陶芸や染色という産業自体はあるけれど、そういった工房は個人の経営がほとんどですよね。なのでどうしても、金沢のような動きにまでは至らないのが現状なのかもしれないですね。
ところで、五月女さんの作品は、東京モード学園のCMに使われているとか。
モード学園 2023年度WEB MOVIE 「好きならば、言え」篇
五月女:はい、大変ありがたいことに、お声がけをいただいて。「こんなことがあるんだ」と、びっくりしました。
今までは作品そのもの、現物で勝負してきたんですけど、私の作品は見た目のインパクトが強いから、今回のようにビジュアルを使うお話もいただけたのかな、と。ビジュアルを使って、“唇”という概念を前に出すような考えは面白いなと思っています。将来的には、本の表紙などでも使っていただけたら良いなぁ、とか。私の夢は、ゆくゆくは化粧品会社とコラボして、広告のビジュアルで作品を使っていただくことなので。それに少しずつ近づいて行っているのかな、と思うと嬉しいですね。
深井:唇をモチーフとして扱っているのは、どういう意図が?
五月女:私がずっとテーマにしているのは「お化粧」なんですよ。特に“赤い口紅を引く”という行為は、私のなかで、すごくお化粧らしい工程だという印象があるから、唇の作品をたくさん作っています。そもそもなぜ、お化粧がテーマなのかというと。漆の制作過程である「塗り重ねて覆い隠す」「磨きをかけていく」というのが、お化粧に似ているなと思って。それで「漆とお化粧って、相性がいいんじゃないか?」と思ったのが、このテーマで制作するようになったきっかけです。百貨店で接客しながらお化粧品のポスターを眺めていたら思いつきました(笑)。
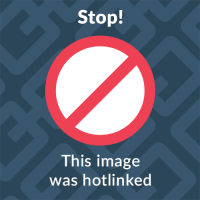
五月女:赤い色には、世間一般としては“強い女性の象徴”というイメージがあると思いますが、私は別に、赤い色やお化粧を「女性だけのものだ」と主張したいわけではないんです。特に最近は男性もお化粧していますし、私が化粧品業界で働いていた当時から、男性の美容部員もいました。私はたまたま女性で、お化粧が楽しくて好きだからやっているだけなので、ほかの方も、男性も、お化粧が好きならば誰でもやったらいい、という想いで制作しています。
あと唇って、実は人間だけにある器官らしいんです。サルにもあるように見えて、あれは人間の唇の構造とは違うみたいなんですね。人間の唇だけが、内皮が成形して器官になっているんです。
それを知って、唇という器官そのものが、非常に人間らしいな、と感じました。言葉を使ったコミュニケーションや、食事、また性欲や愛情を表現するときなど、いずれも人間の欲望にかかわる場面で唇は印象的にはたらきますよね。私は人間にすごく興味があるんですよ。「きれいなところも、きれいじゃないところも知っていきたい」と思っていて。そういった意味もあって、唇というモチーフを非常に気に入っています。
深井:漆はなかなか高価な素材なんですけど、きちんと管理すれば何年ももつし、価値のある作品になるんじゃないかなと思います。今後は海外進出なんかもできるといいですね。頑張ってください。
? ? ?
【後編はこちらから】
? ? ?
(文:城下透子、撮影:法人企画広報課?加藤)
城下透子(しろした?とうこ)
1994年北海道生まれ。東北芸術工科大学芸術学部文芸学科卒業。
株式会社ecloreのSEOサービス『Rank-Quest』内ライティングチームの編集長。同社のライティングサロン「moc塾」講師。在学中に学んだライティングや編集の知識をもとに、現在は株式会社ecloreにて、コラム記事やインタビュー記事などの執筆を手がける。
またチームメンバーが執筆した記事の校正?校閲や、ライティングに関する全体の指導も担当している。
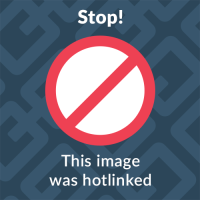
東北芸術工科大学 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-
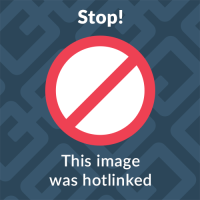
2019.10.25|ニュース&トピックス
まちなかに新しい学生街をつくる/準学生寮プロジェクト
#万博体育投注_万博体育彩票-下载app登录#準学生寮 -
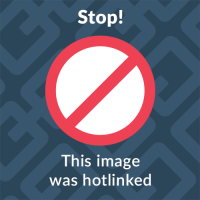
2022.12.14|ニュース&トピックス
学生選抜展 DOUBLE ANNUAL 2023 「反応微熱ーこれからを生きるちからー」/アシスタントキュレーター?千田真尋(文化財保存修復学科2年)
#DOUBLE ANNUAL#イベント#在学生 -
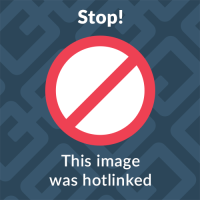
2020.05.11|レポート
国際化する大学病院のサスティナブルデザイン
#デザイン




